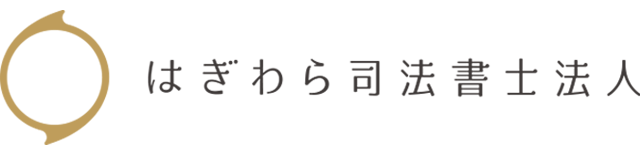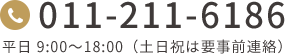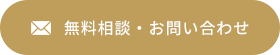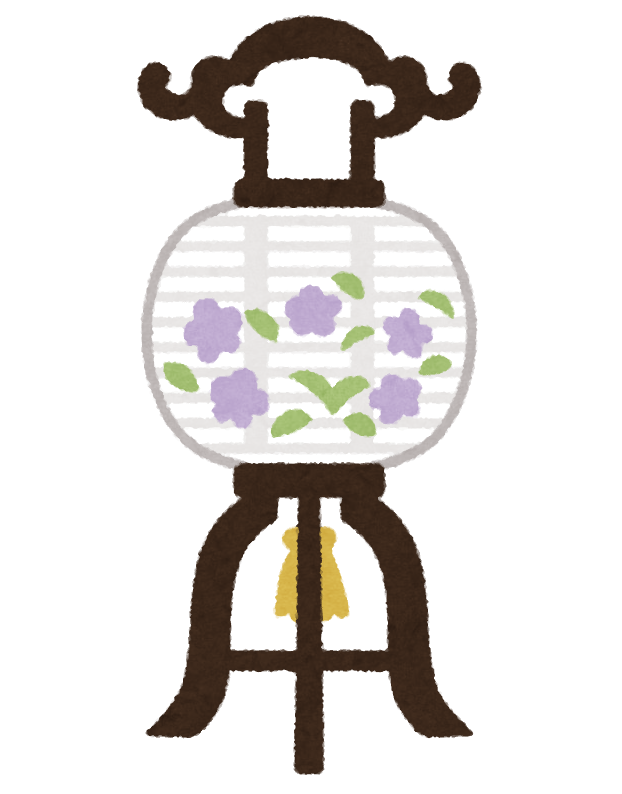お世話になっております。
本日は、前回、前々回に続き、法定相続分での相続登記をする際の注意点について解説致します。
まずは、こちらをお読み下さい。
https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-958.html
https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-965.html
相続登記を申請する際に、名義人として申請人となる方に、法務局から登記識別情報通知が発行されます。
昔で言うところの、権利証(登記済証)と呼ばれる書類です。
登記識別情報通知とは、売却したり、贈与したり、その不動産に抵当権等を設定するときに使用するとても大切な書類です。
売却等の名義変更をする場合や、担保に入れたりする場合に使うもので、再発行もされないものですので、不動産の名義人の方が大切に保管して頂く必要があります。
登記識別情報通知は、不動産を取得する時(本日のテーマだと相続登記を申請する時)、「申請人として登記名義人となる方」に発行されます。
発行される条件として、申請人となる必要があるという事です。
分かりづらいですね。。
例えば…
父が死亡し、母と子一人が相続人である場合に、法定相続分である2分の1ずつ名義を受けようとする時は、母のみが申請人となれば、登記申請することが出来ます。
子に手間を掛けさせない為に、母のみが申請人となれば、母一人で手続きを完結させられるという事です。
ここで、本日のテーマである法定相続分での相続登記をする際の注意点ですが、上記の例の場合、母のみが申請人となるので、母の分のみの登記識別情報通知が発行され、子の分の登記識別情報通知については、発行されないことになります。
売却等名義変更をする場合、子の登記識別情報通知が無い状態で売買に臨むことになります。
売却が出来ないわけでは無いですが、代わりになる書類(本人確認情報と言います。)を作成する必要があるので、費用が掛かります。
相続人の中で協力をしてもらえない方がいる等の事情がある場合は止むを得ないですが、可能であれば、売却等の名義変更の場面で余計な費用を掛けない為にも、名義人となる方全員が申請人として相続登記に関与する方が好ましいという事です。
なんとなくご理解頂けましたでしょうか。。
3回に渡り、法定相続分での相続登記をする場合の注意点について、解説致しました!
はぎわら司法書士法人では、相続手続き、遺言、生前贈与に関するご相談を多数頂いております。
大変有り難い事に、毎日のように新しいご相談を頂いております!
ご連絡をお待ちしております!
よろしくお願い致します!!!!
相続・遺言に関連する記事
生前贈与を受け、相続時精算課税制度を利用する方へ
法改正により、2024年4月から相続登記が義務化されます!!
ただ、そのままご家族が住み続ける等、名義を変更する必要が無ければ、亡く...